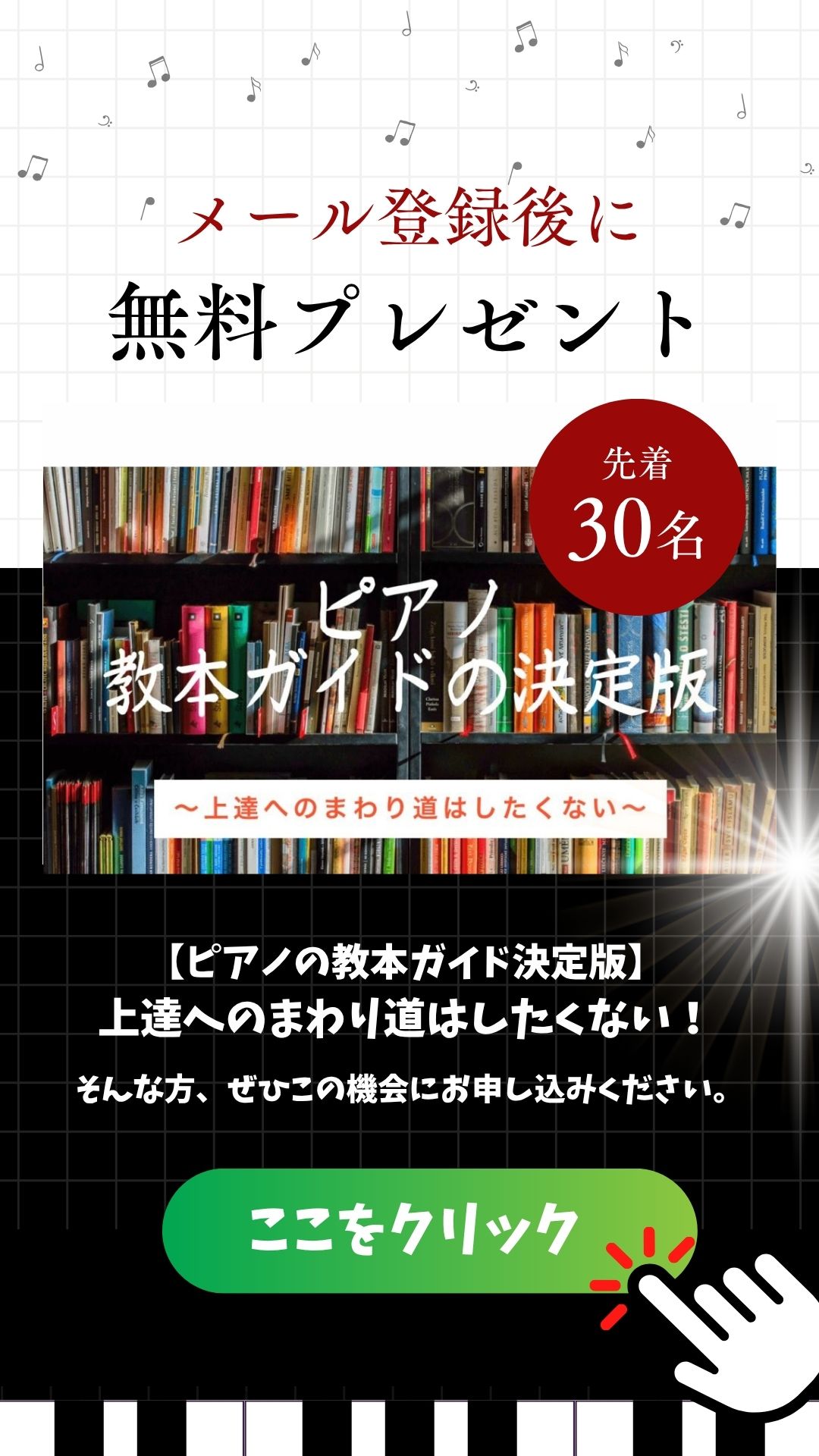ベートーヴェンのピアノ・ソナタをピアノ初心者さんの中には、「初心者だけれど、弾いてみたい」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
大丈夫です、上級者にならないと挑戦できないとことはないんですよ!
「バッハの平均律は“ピアノの旧約聖書”、ベートーヴェンのピアノソナタは“ピアノの新約聖書”」
この有名な言葉は、19世紀の名指揮者ハンス・フォン・ビューローが残した表現です。
ルードヴィヒ・バン・ベートーヴェン。
クラシックを貴族だけのものではなく市民にも身近な存在にし、難聴に苦しみながらもたくさんの傑作を生みだしました。
現在もベートーヴェンの曲は演奏し続けられていますね。
その当時、ピアノ自体が進歩し鍵盤数も拡張され、ペダルも付きました。
ベートヴェンはそのピアノを使って、革新的なピアノソナタを作曲しました。
ピアノ・ソナタの意味を大きく変え、芸術的要素にしたソナタとは、どのように作曲されたのでしょうか。
この記事では、ベートーヴェンの人生を「ピアノ・ソナタ」とともに辿っていきながら、作曲された背景を知って曲に対する理解を深めていきます。
そして、初心者さんにも挑戦できるポイントをお伝えしますね。
ぜひ、最後までお付き合いください。
この記事から分かること
- ベートーヴェンの人生
- 三大ピアノ・ソナタ 「熱情・月光・悲愴」
- 三大ピアノ・ソナタ以外から知るベートーヴェンの人生
ベートーヴェンの人生とピアノ・ソナタ

ベートーヴェンが難聴だったことは有名ですが、どのような人生を歩み、その中でどのようにピアノソナタが生まれたのかを知ると、作品への理解が深まるかもしれません。
ここではベートーヴェンの生涯をたどりながら、どのようにピアノソナタが生まれていったかをご紹介します。
誕生から20代(1770年~)
・ドイツのボンで誕生
宮廷音楽家であった父からは幼少期から厳しい音楽指導を受けます。
12歳にして宮廷楽長不在時にオルガン演奏の代理を務め、14歳からは報酬を与えられるようになりました。
・母親が肺結核で死去
これにより家庭の経済的、家政的な責任がベートーヴェン一人にのしかかります。
父親は絶望からアルコール依存症になってしまいました。
ここで、ベートーヴェンが若き日に起こった印象的な出来事を一つご紹介します。
・ウィーンでモーツァルトに会う
ベートーヴェンがモーツァルトに即興演奏のテーマを与えてくれるように頼み、尊敬する彼の前で熱意を持って演奏しました。
モーツァルトは友人に「いつの日か彼は、語るに足るものを世界に与えるだろう」と声を弾ませて言ったといわれています。
・ボン大学に入学
ハイドンに師事するためにウィーンへ移住しました。
ピアノ三重奏曲Op.1を出版し作曲家デビューを果たしますが、そのころから難聴の兆候が表れ始めます。
ソナタの1番から10番と19番、20番が1795年から1799年までに書かれていますが、初めてのソナタの1番に惹かれます。
| カナの好きな曲 | ピアノ・ソナタ第1番 第1楽章 |
| 理由 | ♭4つのヘ短調は当時としては異質で、ベートーヴェンの「私の音楽はこうだ!」という意気込みを感じられる |
| 読者様へ | 全32曲へと続く第一歩、とても惹きつけられませんか? |
これが、ベートーヴェン初のピアノ・ソナタ第1番です。
引用:YouTube
充実期の30代(1800年~)
交響曲第1番をベートーヴェン自身の指揮で初演し、本格的な作曲活動を行うようになります。
しかし、難聴が進行し「ハイリゲンシュタットの遺書」を書き、苦悩と向き合いながら創作活動を続けました。
・交響曲第3番「英雄」
当初、ナポレオンに献呈する予定でしたが、皇帝即位に失望し、楽譜を破った逸話は有名です。
・ピアノ・ソナタ第23番「熱情」の作曲を開始
この曲の原稿をピアニストのマリー・ビゴーに見せたところ、初見で完全に弾いてしまいます。
ベートーヴェンは大変喜び、出版後の原稿を彼女に贈りました。
この自筆譜は現在、パリ音楽院に保存されています。
充実期では、交響曲第5番「運命」、第6番「田園」などの代表作も初演され、ピアノ・ソナタ第12番から第26番が1810年までに作られていました。
| カナの好きな曲 | ピアノ・ソナタ第13番 第1楽章 |
| 理由 | 友人に難聴を打ち明けた手紙を書いている時期に作曲されたと思えない曲調が好き |
| 読者様へ | 難聴に苦しんでいても天才はスゴイ!って思いませんか? |
引用:YouTube
聴覚を失ってから永眠まで(1810年~)
1810年に聴覚を完全に失いますが、創作意欲は衰えず「エリーゼのために」を作曲(未完)しました。
1821年には、最後のピアノ・ソナタ第32番の作曲を開始します。
54歳の時に交響曲第9番の初演を自身の指揮で行います。
完全に耳が聴こえない中での奇跡的な舞台でした。
アンコールが5回も続き、警察が制止したと言われています。
そして2年後にウィーンで死去、享年57歳でした。
ベートーヴェンの葬儀は、誰も想像できなかったほど盛儀でした。
ウィーン中の音楽家や著名人が参列し、数万人もの市民が参加したと言われています。
| カナの好きな曲 | ピアノ・ソナタ第32番 第1楽章 |
| 理由 | あと5年で亡くなると分かっていたわけではないと思いますが、焦っているように感じます |
| 読者様へ | 最後のピアノ・ソナタ、1番と比べてどう感じますか? |
引用:YouTube
ベートヴェン作曲 三大ピアノ・ソナタに挑戦してみよう!

ベートーヴェンのピアノ・ソナタは、クラシック音楽の中でもとりわけ高く評価される作品群です。
中でも「悲愴」「月光」「熱情」の3曲は、“三大ピアノ・ソナタ”として広く知られています。
三大ピアノ・ソナタについて始める前に、ソナタ形式をおさえておきましょう。
ソナタ形式とは?
ソナタ形式とは楽曲形式のひとつで、「提示部+展開部+再現部」で構成されています。
- 提示部:2つの対照的な主題(メロディ)が提示される
- 展開部:2つの主題が展開、変化する
- 再現部:提示された2つの主題が再現される
ソナタ形式をおさえたところで、三大ピアノ・ソナタ「悲愴・月光・熱情」を見ていきましょう。
いきなり全楽章を弾くのは、ハイレベルなので挑戦しやすい楽章ごとに紹介していきますね。
- 悲愴 第2楽章
- 月光 第1楽章
- 熱情 第2楽章
ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」第2楽章
「悲愴」は、ベートーヴェンが自ら副題を付けた、ピアノソナタ前期の代表作です。
劇的で重厚な第1楽章の序奏には、当時の社会不安や内面の葛藤がにじみ出ているとも言われています。
一方第2楽章は、全体の中でも特に穏やかで抒情的な楽章です。
第1楽章のドラマティックな雰囲気と全く異なる、とても癒される作品です。
- 29歳の時に発表
- パトロンのカール・アロイス・フォン・リヒノフスキー侯爵へ献呈
- 売れっ子作曲家になるターニングポイントになった曲
※初心者向けにアレンジされていますので、原曲とは異なります。
引用:YouTube
繰り返されるモチーフ「ド・シ・ミ」の練習ポイントは2つ
①指使い
・C(ド)=1指(親指)
・B(シ)=2(人差し指)
・E(ミ)=4(薬指)
シからミを弾くときは、指をくぐらせたり無理に伸ばしたりしないよう、手の形を丸く保ってください。
②音のつながりを意識
ド・シ・ミは滑らかにつながるように
それぞれの音を2拍ずつ伸ばして弾いてみて、ペダルなしで繋がって聴こえるかをチェックしてください。
ここで、原曲も聴いてみましょう。
ピアニスト:清塚信也
引用:YouTube
ピアノ・ソナタ第14番「月光」第1楽章
「月光」と呼ばれるようになったのは、ルートヴィヒ・レルシュタープ(詩人)が「湖の月光に揺れる小船のよう」と言ったことが由来です。
この作品は「幻想曲風ソナタ」と題されており、通常のソナタ形式とは異なる自由な構成が特徴です。
第1楽章は拍子は3拍子ですが、舞曲のようなリズムではなく、時間が止まったような静けさと幻想的な響きが漂います。
- 聴覚が衰え始めた30歳ごろに作曲された
- 恋をしていたジュリエッタ・グイチャルディへ献呈
- 楽章が進むにつれテンポが増し、感情の高まりを感じられる
※原曲より、かなり遅いテンポで弾いています。
引用:YouTube
冒頭のメロディはG♯(ソ)、B(シ)、E(ミ)の繰り返しで右手の親指のG#を中心に展開されます。
人差し指B、小指Eとの音量をしっかりと区別しましょう。
ピアノ・ソナタ第23番「熱情」第2楽章
「熱情(アパショナータ)」は、第21番ヴァルトシュタイン、第26番告別とともに人生中期における「傑作の森の時代」のひとつです。
全体の中で唯一、穏やかで静かな時間が流れる楽章です。
シンプルな伴奏の上に、短いメロディが繰り返されながら少しずつ変化していく構成になっています。
強く弾くのではなく、深く語りかけるように音を紡いでみてください。
- 1805年に完成
- オペラ「フェデリオ」の表現を応用したと分かる部分がある
- 「熱情」は後世の出版社が付けた
引用:YouTube
第2楽章の特徴として、ゆったりとしたテンポ(Andante con moto)、メロディがシンプル、複雑なリズムが少ないです。
先ずは、ゆっくりと片手ずつ練習しましょう。
三大ピアノ・ソナタ以外から知るベートーヴェンの人生

三大ピアノ・ソナタを紹介してきましたが、読者様の中には「難しい、もう少し手の届きそうなピアノ・ソナタを弾きたい」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ここからは、三大ピアノ・ソナタ以外から4曲のピアノ・ソナタをベートーヴェンの人生とともに見ていきましょう。
この曲なら挑戦できるかも!と思えるかもしれませんよ。
- 第19番&20番 第1楽章
- 第25番 第2楽章
- 第10番 第1楽章
ピアノ・ソナタ第19番&第20番 第1楽章
対になっている短めで、初心者向けソナタと言われており、最初の一歩にどうぞ。
第4番などの初期のころに書かれた曲で、19番は落ち着いた曲調、20番は対照的で明るい構成になっています。
作曲されたときは、25、6歳のころでウィーンでピアノ協奏曲や即興演奏を披露して、公開演奏会デビューをしていた時期でした。
それぞれの特徴はこのような感じです。
- 第19番…リズムが取りやすく弾きやすい構成、左手も単純な和音が中心
- 第20番…手の動きがシンプルで、音数も少なく、親しみやすいメロディ
第19番 第1楽章
引用:YouTube
引用:YouTube
ピアノ・ソナタ第25番 第2楽章
25番は、「運命」「田園」「皇帝」の大作を生み出していた時期に作曲されました。
第1楽章にかっこうの鳴き声に聴こえる部分があることから「かっこうソナタ」と呼ばれています。
ゴンドラの上で二重奏を歌うような主題が冒頭から8小節目までです。
指先でレガートを意識して、ポジション移動を少なくしましょう。
シ(B)3→ド(C)4→レ(D)5→シ(B)3→ド(C)4→レ(D)5→ソ(G)1→ラ(A)2→シ(B)3→ド(C)4
引用:YouTube
ピアノ・ソナタ第10番 第1楽章
第10番はベートーヴェンがちょうど30歳になる頃に書かれた作品で、交響曲第1番やピアノ協奏曲第1番を初演していました。
軽やかさと温かさを持つ中期初期のソナタで、第1楽章は軽快で明るく、楽しげな雰囲気が魅力的です。
強弱やリズムの変化にメリハリをつけるように弾きましょう!
引用:YouTube
ベートーヴェンのピアノ・ソナタ
ベートーヴェンの人生をピアノ・ソナタから辿ってみました。
彼の作品は時代が関係しているとはいえ、色々な人へ献呈され、感謝の意を表すために作られた作品も多くあります。
最後に記事を振り返ってみましょう。
- 悲愴…モチーフは手の形を保って、繋がるように弾く
- 月光…親指と人差し指・中指の音量の違いを出す
- 熱情…深く語りかけるように弾く
- 第19番 第1楽章…リズムが取りやすい
- 第20番 第1楽章…音数が少なく、親しみやすい
- 第25番 第2楽章…右手のポジション移動を少なくする
- 第10番 第1楽章…強弱やリズムの変化にメリハリをつける
ピアノ・ソナタからベートーヴェンの人生を知ることで、新たな発見はありましたか?
「ベートーヴェンのピアノ・ソナタを弾きたくなった」「もっとベートーヴェンを知りたくなった」と思っていただけたら嬉しいです。
ベートーヴェンの音楽が、あなたの毎日の生活を豊かにしてくれますように!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。