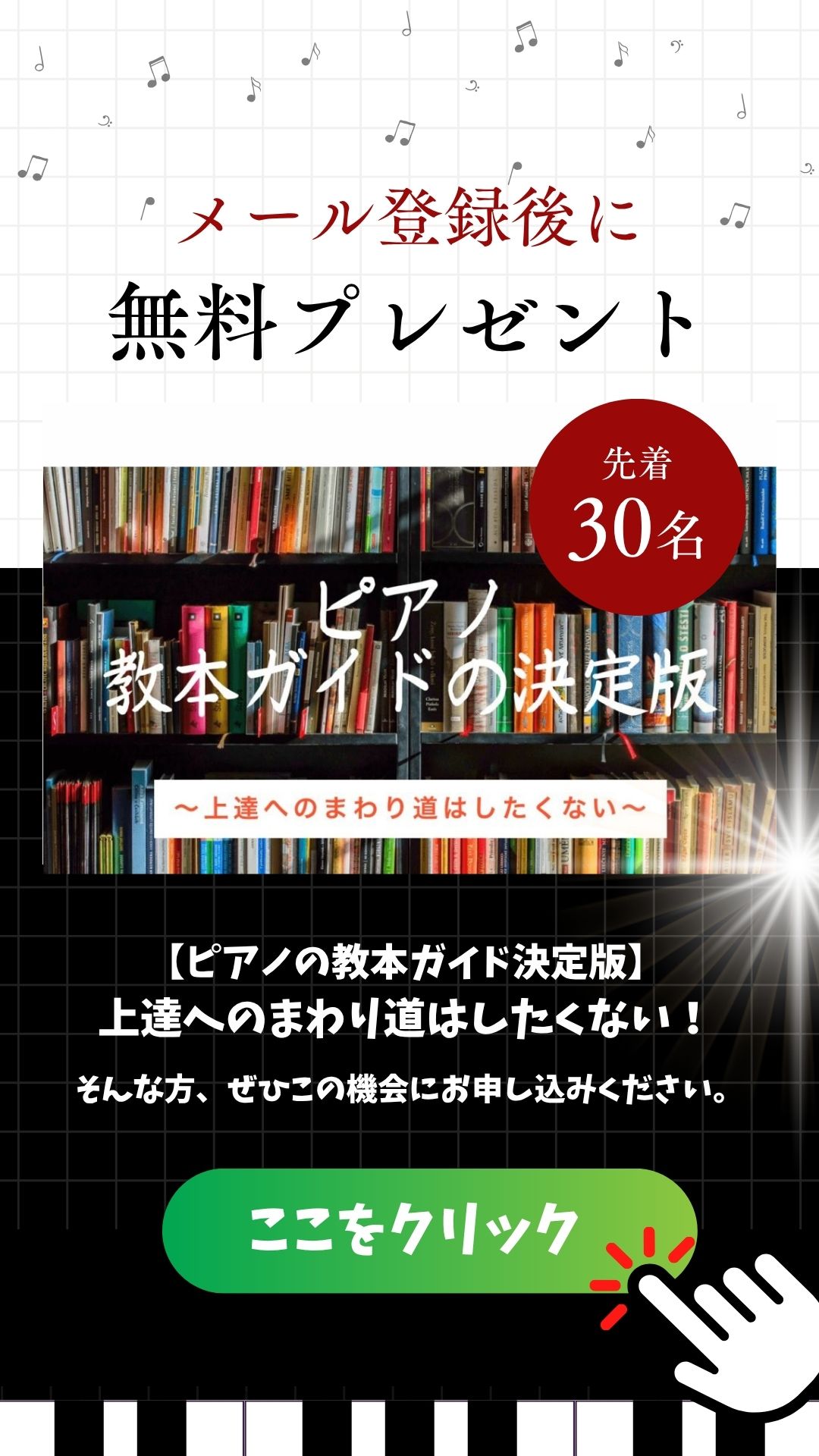読者様は音階練習を毎日の練習メニューに取り入れていますか?
「音階練習って地味だしつまらない」と、挑戦してみたものの継続が難しい練習ですよね。
ですが、音階練習をする明確な目的を決めると達成感が生まれ、次の練習のモチベーションに繋がります。
音階練習は基礎練習の一つです。
メイン曲を練習する前に指の準備運動として取り入れてはいかがでしょうか。
この記事では、なぜ音階練習が初心者や練習中の人に最適なのかを解説します。
・ピアノ音階練習をする目的
・ピアノ音階練習をする際の注意点
・ピアノ音階をマスターする効果的な練習方法
音階の反復練習を毎日の練習に加えて、演奏技術の向上に役立てましょう。
ピアノ音階練習の目的
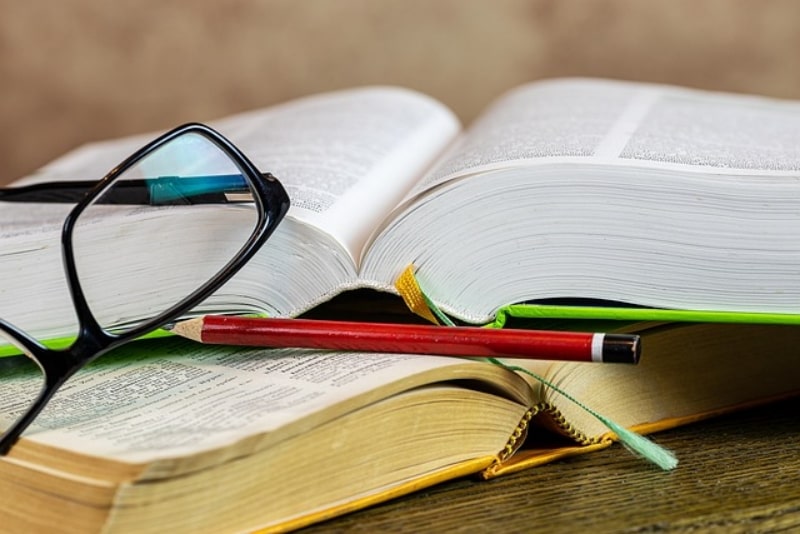
音階練習はなぜ必要なのでしょうか?
大きな理由を一つ上げると、音程感が身につくからです。
他にも、曲を弾いているときに確認しにくい指の並べ方や音色、指と指の感覚はどのくらい空くのかなどの確認に音階練習が有効になります。
音階を練習する目的は3点あります。
- ピアノ演奏に必要な基本的技術を身につけるため
- 曲の構成や調性を理解するため
- 自分の表現力や想像力を高めるため
音階練習は一音一音の質を高めるための基礎練習です。
指の動きをトレーニングすることで演奏技術が飛躍的に上達します。
ぜひ、曲の練習をする前にウォーミングアップとして取り入れてみてください。
音階の練習は闇雲にするのではなく、具体的な目的を持って練習することが大切です。
音階練習の基本
音階練習は、どちらの手でも十分弾けるようになることが基本です。
どちらの手でも同じように弾けるようにならないと、両手で練習しても上手に弾けません。
まずは片手から、左右どちらの手でも同じように弾けるようになったら両手でも練習します。
そのとき左右対称の形での練習が基本です。
きちんと一音ずつ耳で確認しながら、間違いなく弾けるようになるまで繰り返し練習しましょう。
音階練習の動画は、YouTubeにもたくさん上がっています。
私がよく利用している清塚信也さんのYouTube動画は、指運びをわかりやすく載せてくれているので参考にしてみてください。
引用:YouTube
ピアノの音に気をつけながら練習すれば、指使いやリズム感、耳のトレーニングに役立ちます。
音階練習する際の注意点
音階練習する際に注意するポイントが5つあります。
- 脱力を意識する
- 指先をしっかり鍵盤に押し付ける
- 指の形を崩さない
- テンポを一定に保つ
- 音程や音色を聞き分ける
安定して弾くためには、手首を正しく使って動かす必要があります。
正しいフォームで指の力を調整し、自然な形で動かせているかチェックしながら練習しましょう。
鍵盤を端から端まで弾くときの体重移動もスムーズにできるようになるといいですね。
はじめはゆっくり弾き、徐々にテンポを早めて練習します。
どの指で鍵盤を弾いても音が揃うように自分の手にあった指運びを見つけましょう。
音階をマスターするための5つの効果的なトレーニング
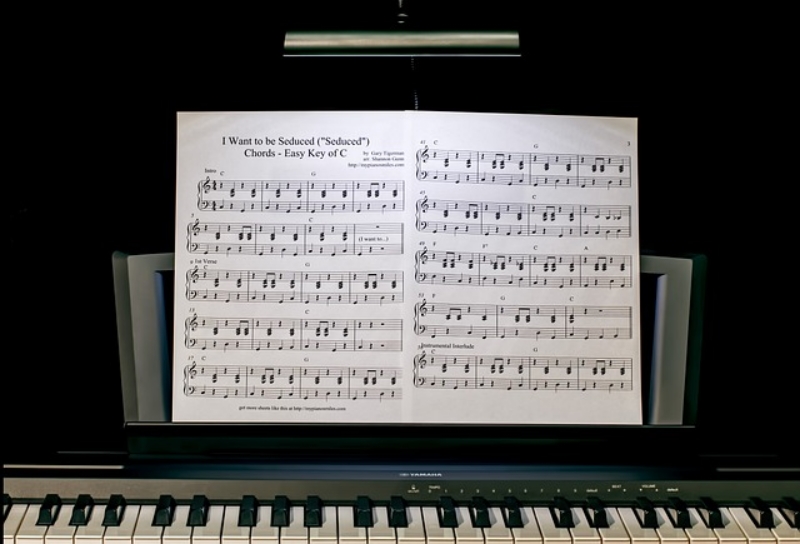
音階をマスターするために5つの効果的なトレーニング法を紹介します。
- 音階の規則性を理解する
- 音階の構成音を覚える
- 音階のパターンや変化形を覚える
- メトロノームを使う
- 音階を曲に応用する
一つずつ解説していきます。
音階の規則性を理解する
音階はさまざまな種類が存在し、日本では民謡や演歌、雅樂といった独自の文化から生まれた音楽に用いられる音階もあります。
代表的な音階には、全音階と半音階、全音音階があります。
全音階は、一オクターブを5つの全音と2つの半音で満たす音階です。
半音階はすべて半音の間隔の音階になります。
半音階とは対称的に全音のみで1オクターブを6等分した音階が、全音音階です。
※全音とは、鍵盤2つ分の距離を指す。「ドとレ」、「ミとファ♯」など
半音とは、鍵盤一つ分の距離を指す。「ドとド♯」、「ミとファ」など
音階を理解することは演奏技術の向上に役立ちます。
音階の構成音を覚える
音階の構成音は実際にピアノを弾きながら耳で覚えるのが効果的です。
繰り返し練習することで自然に耳がなじんできます。
最初はゆっくり、音を間違えないように丁寧に、徐々にテンポを早めていきましょう。
音階のパターンや変化形を覚える
音階の練習は反復練習が大事です。
まず、基本的なパターンを繰り返し練習することで指の動きを覚えます。
次に、半音階を追加していき様々な音階パターンを練習します。
基本的なパターンから徐々に複雑なパターンや変化を加えていくことで自然に演奏できるようになりますよ。
メトロノームを使う
メトロノームを使うことで正確なリズム感覚を養います。
メトロノームは、練習の際にリズムを維持するため非常に役立ちます。
特に初心者や練習中の人は、リズム感やタイミング、テンポコントロールなど演奏スキルの向上が見込まれます。
音階を曲に応用する
たくさんの音階が含まれた曲は練習に最適です。
そこで、音階練習に最適な曲を3曲紹介します。
- ベートーヴェン「月光のソナタ」
引用:YouTube
この曲には様々な音階が含まれており音階練習におすすめです。
第1楽章の冒頭に現れる音階が有名ですね。
ホ短調の3オクターブに渡る印象的な降下音階で「月光」という愛称がつけられています。
また、第2楽章にもたくさんの短調の音階が含まれています。
- チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番」
引用:YouTube
オーケストラと共に演奏される曲ですが、多くの音階が含まれており技術的な向上に役立ちます。
有名なところでは第2楽章冒頭に右手で演奏される美しい音階はイ長調のなめらかな上昇音階です。
また、第三楽章中間部に左手で演奏されるト短調の音階があります。
全体的に技巧的で、演奏技術を高めるのに有効な練習曲です。
- バッハ「インべンションとシンフォニア」
引用:YouTube
「インベンションとシンフォニア」はインベンション15曲とシンフォニア15曲の計30曲からなる曲集です。
この作品はバッハが息子の音楽学習のために作った曲で、ピアノ初心者や愛好家が多声をきれいに弾き分けられることを目指して作曲したといわれています。
その中でも前半のインベンションは、左右の手を独立して練習するのに最適です。
「インベンション第1番」には、シンプルながら効果的なイ短調の降下音階があります。
この音階は曲全体にわたって繰り返されており、非常に印象的な効果を生み出しています。
他にも「インベンション第4番」のリズミカルでエネルギッシュなイ短調の上昇音階や「インベンション第8番」の緩やかなメロディによるイ長調の上昇音階などがあります。
これらの音階を練習することで音楽理論の理解や演奏技術の向上に役立ちます。
音階練習でステップアップしよう
音階練習は演奏技術を向上させるために有効な方法です。
音階を練習すれば正しいフォームやスムーズな指運びが身につきます。
- 脱力を意識する
- 指先をしっかり鍵盤に押し付ける
- 指の形を崩さない
- テンポを一定に保つ
- 音程や音色を聞き分ける
音階練習の効果を上げるには、ピアノの音を意識しながら毎日の積み重ねが大事です。
音階をマスターするためのトレーニング方法を紹介しました。
- 音階の規則性を理解する
- 音階の構成音を覚える
- 音階のパターンや変化形を覚える
- メトロノームを使う
- 曲に応用する
音階練習に最適な曲は、紹介した曲以外にもたくさんあります。
ぜひたくさんの音階パターンを体感して演奏レベルを上げていきましょう。
こちらの記事では、毎日の練習の仕方や時間の目安などを解説しています。
ピアノの練習って毎日した方がいいらしいけど、どのくらい・どうやってやればいいの?もっと効率的にできないかな?とお悩みの読者様。当記事で一気に解決します。ご自身の練習法をチェックして、即改善できるアドバイスをご用意していますので是非ご一読を♪
ぜひ、併せて読んでみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。